【小学生の勉強を習慣化する5つのコツ】勉強時間の目安や習慣化のメリットも解説!
- ゲームやYouTubeばかりで勉強は後回し…。
- 毎日「勉強しなさい!」と言わないと宿題も終わらない…。
- どうすれば自分から机に向かってくれるんだろう?
子どもに勉強習慣を身につけさせるのは想像以上に難しいものです。無理に勉強させると、子どもが「勉強嫌い」になったり、親子関係が悪化したりする可能性があります。子どもを無理やり机に向かわせても、理想的な勉強習慣は身につきません。
この記事では、小学生の勉強を習慣化するための5つのコツを解説しています。この記事で解説していることを実践すれば、子どもに勉強習慣を身につけさせるための適切なサポートができます。子どもに勉強習慣を身につけさせたい人は、最後まで読んで習慣化のコツをマスターしてください。
小学生の勉強時間の目安は「学年×10〜15分」

小学生の勉強時間の目安は「学年×10〜15分」です。3〜5分くらいの勉強から始めて、少しずつ目安の時間に近づけていきましょう。
ただし、子どもによって集中できる時間は違うので、目安の勉強時間に強くこだわる必要はありません。下記の表を目安にしながら、子どもの様子を見て、無理なく続けられるよう勉強時間を調整してください。
| 学年 | 勉強時間の目安(学年×10〜15分) |
|---|---|
| 1年生 | 10〜15分 |
| 2年生 | 20〜30分 |
| 3年生 | 30〜45分 |
| 4年生 | 40〜60分 |
| 5年生 | 50〜75分 |
| 6年生 | 60〜90分 |
ベネッセ教育総合研究所の「子どもの生活と学びに関する親子調査2022」によると、小学校1~3年生の勉強時間の平均は48分。小学校4〜6年生の勉強時間の平均は78分です。「学年×10〜15分」を目安に勉強習慣を身につけておけば、学年相応の学力を維持するのに十分な勉強時間を確保できます。
| 学年 | 学校外の勉強時間(平均) |
|---|---|
| 小学校1〜3年生 | 48分 |
| 小学校4〜6年生 | 78分 |
» ベネッセ教育総合研究所「子どもの生活と学びに関する親子調査2022」(外部サイト)
小学生の勉強を習慣化するための5つのコツ

勉強の習慣化には明確なコツがあります。勉強をスムーズに習慣化するための5つのコツを解説します。
①毎日同じ時間・タイミングで勉強する
毎日同じ時間・タイミングで勉強することで、習慣として定着しやすくなります。手洗いや歯磨きのように「同じ時間になると同じことをしたくなる」という脳の仕組みが働くからです。
例えば、「朝7:30から15分勉強」「おやつを食べたら30分勉強」と具体的に時間やタイミングを決めておきましょう。午後に勉強する場合は、タイミングを固定するのがおすすめです。「おやつの後」「友達と遊ぶ前」と決めておけば、行事や習い事で帰宅時間がずれても、勉強を始めるまでの流れを一定にできます。
②勉強時間を固定する
習慣を定着させるには、勉強場所を固定することも重要です。毎日同じ場所で勉強すると「この場所に座ったら勉強する」と無意識に行動のスイッチが入るようになるからです。
勉強場所は学習机でもリビングテーブルでも構いません。ただし、ゲームや漫画といった集中を妨げるものは見えないようにしておきましょう。集中しやすい環境を整え、「ここは勉強する場所」と決めておけば、座るだけで勉強スイッチが入るようになります。
やることを具体的に決める
勉強内容は具体的に決めておきましょう。脳はあいまいなことを嫌うため、やることが明確でない活動を無意識に避けてしまうからです。
例えば、「漢字ドリルを1ページ」「計算問題を10問」と具体的に決めて、ホワイトボードなどに書いておきます。すぐに勉強を始められるので、習慣として定着しやすくなります。「20分勉強したら5分休憩」と休憩時間も決めておくと、メリハリがついて集中力が持続するのでおすすめです。
④成果を見えるようにする
勉強した後は、学習内容をノートに記録したり、カレンダーにシールを貼ったりして成果を「見える化」しましょう。「こんなにできたんだ」という自信になり、勉強へのモチベーションを保てるからです。
特におすすめなのが、勉強したらカレンダーにシールを貼る「カレンダー&シール」という方法です。普段使っているカレンダーにシールを貼るだけなので手軽に始められます。一度始めると「途切れさせたくない」という意識が生まれるので、勉強を継続する強い動機付けになります。
⑤「簡単すぎる行動」から始める
習慣化を成功させるには、「簡単すぎる行動」から始めることが大切です。脳は「いつもと同じ」を好み、新しい習慣を嫌がる性質があるからです。「簡単すぎる」と感じるくらいの小さな行動なら、脳の抵抗を受けずに習慣化をスタートできます。
最初は「3分だけ」「1問だけ」の勉強で十分です。毎日続けることを最優先にして、簡単に達成できる小さな行動を積み重ねましょう。1ヶ月程度続けて勉強習慣が身についてから、少しずつ勉強時間を伸ばしてください。
【学年別】習慣化させやすいおすすめの勉強法

発達段階や学年によって、重視すべきポイントや取り組みやすい勉強内容は異なります。習慣化させやすいおすすめの勉強方法を学年別に解説します。
【1・2年生】「親と一緒に宿題をする」
低学年の家庭学習は、宿題に一緒に取り組むだけでも十分です。子供がもっとやりたいという場合は、短時間で終わる簡単なドリルを取り入れるとよいです。内容よりも勉強習慣をつけることを優先してください。
低学年の子どもが勉強を習慣化するためには、親のサポートは必須です。親がそばで見守り、わからないことをすぐに聞けるようにすることで、低学年の子どもでも安心して勉強できます。さらに「1問ずつ丸をつける」「できたらすぐ褒める」の2つを意識すると、達成感を得られて勉強へのモチベーションを維持できます。
【3・4年生】「パターンを決めて勉強を習慣化」
中学年になると理科や社会といった暗記が必要な教科が増え、国語や算数でも抽象的な概念が出てきてつまずきやすくなります。授業の復習をして、わからないことをそのまま放置しないことが大切です。
曜日ごとに勉強する教科を決めておくと、1日の勉強量を増やさなくても、無理なく予習・復習ができます。たとえば、「月曜日は算数の文章題」「火曜日は社会」「水曜日は理科」といったように、あらかじめパターンを決めておくと習慣化しやすくなります。
中学年からは、親が直接勉強を教えることを少なくし、自分で学ぶ心構えを育てていくことが大切です。しかし、まだ親の手助けも必要です。家庭学習の計画表を一緒に作ったり、わからないときの解決法を教えたり、いつでもサポートできる距離で見守ってあげましょう。
【5・6年生】「基礎学習+自主学習」
5・6年になると自主学習ができるようになります。好きなことに取り組める自主学習は、勉強へのモチベーションを持続しつつ、自ら学ぶ姿勢も育ててくれます。
たとえば、前半は計算や漢字といった基礎的な勉強、後半は得意な教科や好きなことを調べる時間と基礎的な学習と区別して自主学習の時間を作りましょう。好きや得意を伸ばすことは自己肯定感を高める上でも大きなメリットがあります。
高学年になると、学習内容がより抽象的で複雑になってきます。親が直接勉強を教えると、学校や塾と異なる説明をして子どもを混乱させてしまうリスクがあります。家庭では、学習しやすい環境づくりや心理的なサポートといった間接的なフォローをする方が効果的です。
小学生のうちに勉強を習慣化するメリット3選

小学生のうちに勉強習慣を身につけておくことには大きなメリットがあります。勉強習慣によって得られる3つのメリットを解説します。
①「勉強嫌い」を防げる
勉強習慣が身についている子は「勉強嫌い」になりにくいです。勉強習慣があると必然的に勉強量が増え、「読める漢字が増えた」「計算が早くなった」といった成功体験が生まれるからです。成功体験の積み重ねがあれば自信がつき、学習内容が難しくなっても前向きに勉強に取り組めるようになります。
②中学受験で有利になる
勉強習慣は、中学受験の合否を大きく左右します。競争の激しい中学受験では、どうしても勉強量が必要になるからです。自然に机に向かえる子と、嫌々勉強する子では、勉強量に差がついて当然です。中学受験をしない場合も、勉強習慣があれば着実に学力を伸ばせるので、高校・大学受験で大きなアドバンテージになります。
③「中1ギャップ」を乗り越えられる
学習の遅れが要因の一つとされる「中1ギャップ」は、勉強を習慣化しておくことで乗り越えやすくなります。授業スピードが上がったり、大きな環境変化があったりしても、勉強習慣があれば学習の遅れが生まれにくいからです。小学生のうちに勉強習慣を身につけておくと「中1ギャップ」対策にもなります。
中学校進学時に学習面や生活面、人間関係などの急な変化に戸惑い、不適応を起こしてしまう現象のこと。中学生になると「授業スピードが速くなる」「定期テストがある」「自主的な勉強が求められる」といった学習面での大きな変化がある。
5つのコツで小学生の勉強は習慣化できる!
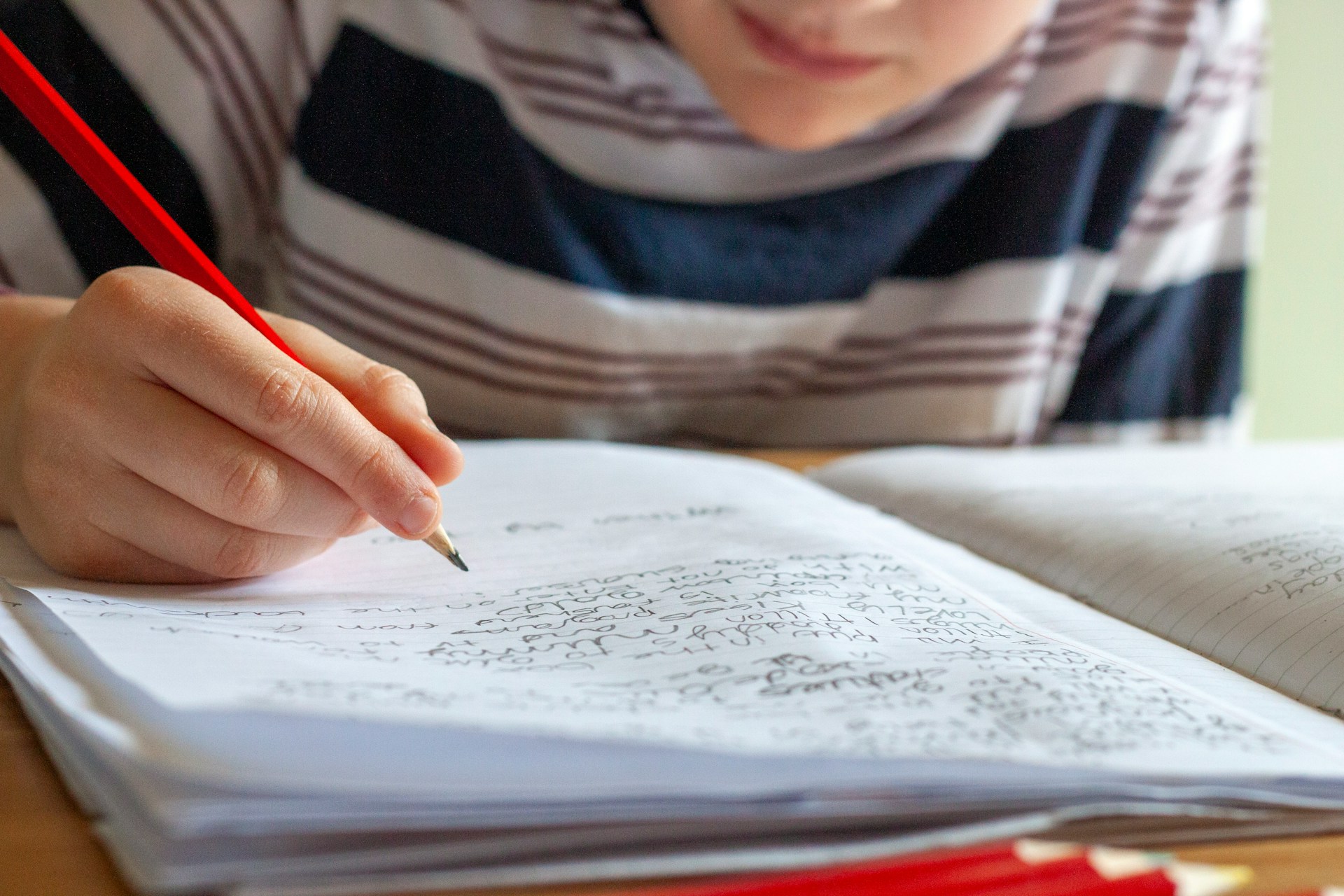
習慣化のコツを知っていれば、子どもに勉強習慣を身につけさせるのがぐっと簡単になります。当記事で解説した習慣化の5つのコツを活用し、今日から勉強の習慣化を始めてみましょう。小さな積み重ねが、子どもの将来を支える勉強習慣の形成につながります。



